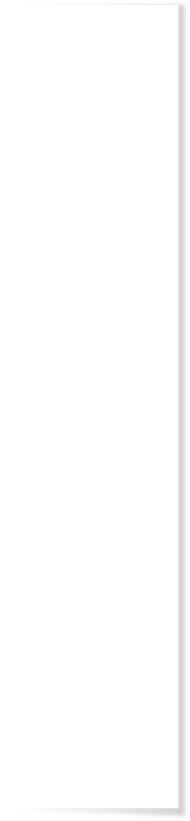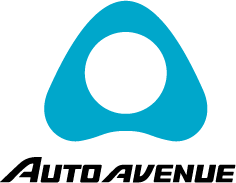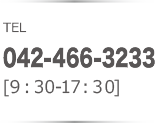バッテリー上がりの原因は?うっかりミスから意外な故障まで、プロが徹底解説!【完全保存版】

目次
はじめに:ある日突然訪れる「バッテリー上がり」という悪夢
いつものように仕事や買い物に出かけようと車のキーを回す。しかし、聞こえてくるのは「キュルキュル…」という弱々しい音か、あるいは完全な沈黙。メーターパネルの明かりも心なしか暗い…。多くのドライバーが一度は経験するであろう、この絶望的な瞬間こそ「バッテリー上がり」です。
AFの出動理由で毎年不動の1位を誇るこのトラブルは、まさに誰の身にも起こりうる、最も身近な車の不具合と言えるでしょう。急いでいる時に限って起こるため、パニックに陥ったり、その日の予定が全て台無しになってしまったりと、精神的なダメージも大きいものです。
「なぜ、バッテリーが上がってしまったのだろう?」
「昨日までは普通に動いていたのに…」
多くの人がそう思うはずです。しかし、バッテリー上がりは決して突然起こるわけではありません。その背景には、必ず何らかの「原因」が隠されています。その原因は、ライトの消し忘れといった単純な「うっかりミス」から、日々の運転習慣、さらには車の部品の劣化や故障まで、実に多岐にわたります。
この記事では、車の心臓部ともいえるバッテリーがなぜ上がってしまうのか、その考えられる全ての原因を、初心者の方にも分かりやすく、そして深く掘り下げて徹底的に解説していきます。原因を正しく理解することは、再発を防ぐための最良の策です。この記事を読み終える頃には、あなたはバッテリートラブルに怯えることなく、安心してハンドルを握れるようになっているはずです。さあ、バッテリー上がりの謎を解き明かす旅に出かけましょう。
そもそも「バッテリー上がり」とは?車の心臓部の基礎知識
原因を探る前に、まずは「バッテリー」そのものと「バッテリー上がり」という現象について、基本的な知識を整理しておきましょう。ここを理解するだけで、後の章の解説がすんなりと頭に入ってきます。
車のバッテリーが担う重要な役割
車のボンネットを開けると、多くの場合、箱型の部品が鎮座しています。これが「バッテリー」です。バッテリーは、車に搭載された「充電式の大きな電池」だと考えてください。その役割は大きく分けて2つあります。
- エンジンを始動させるための電力供給
エンジンを始動させるためには、「セルモーター(スターターモーター)」という部品を力強く回す必要があります。このセルモーターを動かすために、瞬間的に非常に大きな電力が必要です。バッテリーの最も重要な仕事が、この始動時の電力供給なのです。 - 電装品への電力供給
ヘッドライト、カーナビ、オーディオ、エアコン、パワーウィンドウなど、現代の車には数多くの電気で動く部品(電装品)が搭載されています。バッテリーは、これらの電装品に安定して電力を供給する役割も担っています。特にエンジン停止中は、全ての電装品がバッテリーの電力だけで動いています。
「バッテリーが上がる」とは、どういう状態?
では、「バッテリーが上がる」とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか。
これは非常にシンプルで、「バッテリーの消費電力が、蓄電量(充電されている電気の量)を上回ってしまった状態」のことです。
スマホのバッテリーで例えると分かりやすいでしょう。充電せずに動画を見続けたり、アプリを使い続けたりすると、やがて充電が切れて電源が落ちてしまいます。これと全く同じことが、車でも起こるのです。
車には「オルタネーター」という発電機が搭載されており、エンジンが動いている間はこのオルタネーターが発電し、バッテリーを常に充電しています。つまり、通常は「消費」と「充電」のバランスが取れているため、バッテリーの電気がなくなることはありません。
しかし、何らかの原因でこのバランスが崩れ、「充電量 < 消費量」という状態が続くと、バッテリーの蓄電量はどんどん減っていき、ついにはエンジンを始動させるだけの力も残っていない「バッテリー上がり」の状態に陥ってしまうのです。
バッテリーが上がった時に現れる代表的な症状
バッテリーが上がると、車は様々なサインを発します。以下に代表的な症状を挙げます。
- ・エンジンがかからない
キーを回しても「カチッ」という音がするだけ、あるいは「キュルキュル…」と弱々しい音がしてエンジンが始動しない。これは最も典型的で分かりやすい症状です。 - ・メーターパネルや室内灯が暗い、または点灯しない
バッテリーの電力が不足しているため、全てのライト類が暗くなります。 - ・ヘッドライトが暗い
エンジン始動前にライトを点灯させてみて、いつもより明らかに暗い場合は要注意です。 - ・パワーウィンドウの動きが遅い、または動かない
パワーウィンドウも電気で動いているため、動作が鈍くなります。 - ・キーレスエントリーが作動しない
リモコンキーを押してもドアのロック・アンロックができない場合も、バッテリー上がりが疑われます。
これらの症状が見られたら、ほぼバッテリー上がりが原因と考えてよいでしょう。次の章からは、なぜこのような事態に陥ってしまうのか、その具体的な原因を一つずつ見ていきます。

【うっかりミス編】誰にでも起こりうる!最も多いバッテリー上がりの原因
バッテリー上がりの原因として、最も多く、そして誰もが経験する可能性があるのが「うっかりミス」によるものです。自分では気づかないうちに、バッテリーの電力を大量に消費してしまっているケースです。
ライト類の消忘れ(ヘッドライト・ルームランプ・ハザード)
JAFの出動理由でも常に上位にランクインするのが、このライト類の消し忘れです。
最も電力を消費するのがヘッドライトです。最近の車は、エンジンを切ると自動でライトが消える「オートライト機能」が標準装備されていることが多いですが、古い車種や手動でライトを操作した場合には消し忘れが起こりえます。
特に、夕暮れ時やトンネル内でライトを点灯させ、目的地に到着した際に消し忘れるというケースが後を絶ちません。ハロゲンランプの場合、わずか3~5時間程度でバッテリーが上がってしまうこともあります。
「ルームランプくらいで?」と思うかもしれませんが、これも立派な原因です。夜間に車内で探し物をしたり、子供をチャイルドシートに乗せたりした際に点灯させ、そのまま消し忘れてしまうケースです。
消費電力はヘッドライトほど大きくありませんが、一晩(8~10時間)つけっぱなしにすれば、バッテリーが上がってしまう可能性は十分にあります。スイッチが「ON」の位置になったままだと、ドアを閉めても点灯し続けるため注意が必要です。
スモールランプ(車幅灯)も意外な伏兵です。ヘッドライトを消したつもりが、一段階だけ回し足りず、スモールランプが点灯したままだった、というケースもよくあります。
また、駐車禁止場所での短時間の停車などでハザードランプを点灯させ、そのまま長時間放置してしまうのも危険です。これらもルームランプと同様、一晩でバッテリーを空にしてしまう力を持っています。
半ドアによるルームランプの常時点灯
自分ではしっかりドアを閉めたつもりでも、完全に閉まりきっていない「半ドア」状態。これもバッテリー上がりの大きな原因です。
多くの車では、ドアが開いているとルームランプが点灯するように設定されています。半ドアの状態では、車は「ドアが開いている」と認識し続け、ルームランプを点灯させ続けます。ドライバーは車を離れてしまうため、この事実に気づきにくいのが厄介な点です。
特に後部座席や荷室のドアは、運転席から確認しづらいため、半ドアになっていないか降車時に確認する習慣が大切です。
アクセサリー(ACC)電源の切り忘れ
車のキースイッチ(あるいはプッシュスタートボタン)には、いくつかの段階があります。
- ・LOCK/OFF
全ての電源が切れている状態 - ・ACC(アクセサリー)
エンジンは停止しているが、オーディオやカーナビ、シガーソケットなどが使える状態 - ・ON
エンジンは停止しているが、全ての電装品が使える状態(エンジン始動直前の状態) - ・START
エンジンを始動させる
問題となるのが「ACC」の状態です。例えば、待ち合わせの時間調整やキャンプなどで、エンジンをかけずに音楽を聴いたり、DVDを見たりすることがあるでしょう。短時間であれば問題ありませんが、これを1~2時間以上続けると、バッテリーの電力を大きく消費してしまいます。
特に大画面のナビや高性能なオーディオシステムを搭載している車は、消費電力が大きいため、より注意が必要です。エンジン停止中の電装品の使用は、バッテリーの電気を直接使っているという意識を持ちましょう。
スマートキーの車内放置とキーの抜き忘れ
現代の車で増えているのが、スマートキーに関するトラブルです。
スマートキーは、常に微弱な電波を発信して車と通信しています。キーが車内や車のすぐ近くにあると、車側も「いつでも発進できる準備をしよう」と待機状態(スリープモードにならない)になり、通常よりも多くの電力を消費し続けます。これを「暗電流(待機電力)の増加」と呼びます。
スペアキーを車内に置きっぱなしにしたり、自宅の駐車場で玄関のキーボックスと車が近い距離にあったりすると、知らず知らずのうちにバッテリーが消耗していくことがあります。
また、従来のキーシリンダー式の車でも、キーをACCやONの位置で抜き忘れると、当然ながら電力を消費し続けます。
これらの「うっかりミス」は、少し注意を払うだけで防げるものがほとんどです。降車時の確認を習慣づけることが、トラブル回避の第一歩となります。
【車の使い方編】知らず知らずのうちにバッテリーを酷使する運転習慣
目に見えるミスだけでなく、日々の車の使い方がバッテリーの寿命を縮め、バッテリー上がりのリスクを高めていることがあります。ここでは、バッテリーに負担をかける運転習慣について解説します。
「ちょい乗り」の繰り返しがバッテリーを弱らせる
「毎日の買い物で、片道5分のスーパーに行くだけ」
「週末に近所の子供の送り迎えに使うだけ」
このような、短時間・短距離の走行、通称「ちょい乗り」は、実はバッテリーにとって非常に過酷な環境です。
思い出してください。バッテリーはエンジン始動時に最も大きな電力を消費します。そして、エンジンがかかっている間にオルタネーター(発電機)が発電し、消費した分の電力をバッテリーに充電します。
重要なのは、エンジン始動で消費した電力を回復するには、ある程度の走行時間が必要だということです。一般的に、約30分以上の連続走行が必要と言われています。
「ちょい乗り」の場合、
- エンジン始動で大量の電力を消費する。
- わずか5~10分走行してエンジンを止める。
- この短い時間では、オルタネーターが発電する充電量が、始動時に消費した量に追いつかない。
この「消費>充電」のサイクルを繰り返すことで、バッテリーの蓄電量は少しずつ、しかし確実に減っていきます。まるで、穴の空いたバケツに少しずつしか水を注がないようなものです。やがてバケツは空になり、ある日突然、バッテリー上がりとして症状が現れるのです。
車の長期間放置による「自己放電」と「暗電流」
「車に負担をかけないように、あまり乗らないようにしている」というのは、実は逆効果です。車は、長期間動かさないことでもバッテリーが上がってしまいます。その原因は「自己放電」と「暗電流」です。
バッテリーは、何も接続していなくても、化学的な作用によって自然に少しずつ電力を失っていきます。これを「自己放電」と呼びます。乾電池を長期間放置すると使えなくなるのと同じ原理です。特に気温が高い夏場は、化学反応が活発になるため自己放電が進みやすくなります。
さらに厄介なのが「暗電流(あんてんりゅう)」です。これは、エンジンを停止し、キーを抜いた状態でも、車の機能を維持するために常に流れ続けている微弱な電流のことです。
例えば、以下のような機能のために電力が消費されています。
- ・カーナビやオーディオの設定の記憶
- ・時計
- ・セキュリティシステム
- ・キーレスエントリーの受信待機
これらの暗電流は、正常な状態であればごくわずかなので、数週間程度の放置でバッテリーが上がることはありません。しかし、1ヶ月以上など長期間にわたって車を動かさないと、自己放電と暗電流の積み重ねによって、バッテリーの蓄電量が空になってしまうのです。出張や旅行で長期間家を空ける際や、セカンドカーであまり乗らない車は特に注意が必要です。
渋滞中や停車中の電装品の使いすぎ
エンジンがかかっていれば充電されるから安心、というわけではありません。特に、エンジンの回転数が低いアイドリング状態では、オルタネーターの発電能力も低下します。
夏の猛暑日や冬の極寒日に、大渋滞にハマっている状況を想像してみてください。
- ☆夏: エアコンを最大風量で稼働させ、カーナビでテレビを見ながら、スマホを充電し、音楽を大音量で聴いている。
- ☆冬: ヒーターとデフロスター(曇り止め)をフル稼働させ、シートヒーターもONにし、ヘッドライトを点灯させている。
このような状況では、アイドリング時の低い発電量が、電装品全体の高い消費電力に追いつかなくなることがあります。つまり、エンジンがかかっているにもかかわらず「充電量 < 消費量」の状態に陥り、バッテリーに蓄えられた電気を消費し始めてしまうのです。
渋滞を抜けて走り出せば回復しますが、このような状況が頻繁に続くと、バッテリーへの負担は蓄積していきます。
【経年劣化・故障編】見逃し厳禁!物言わぬ部品からのSOS
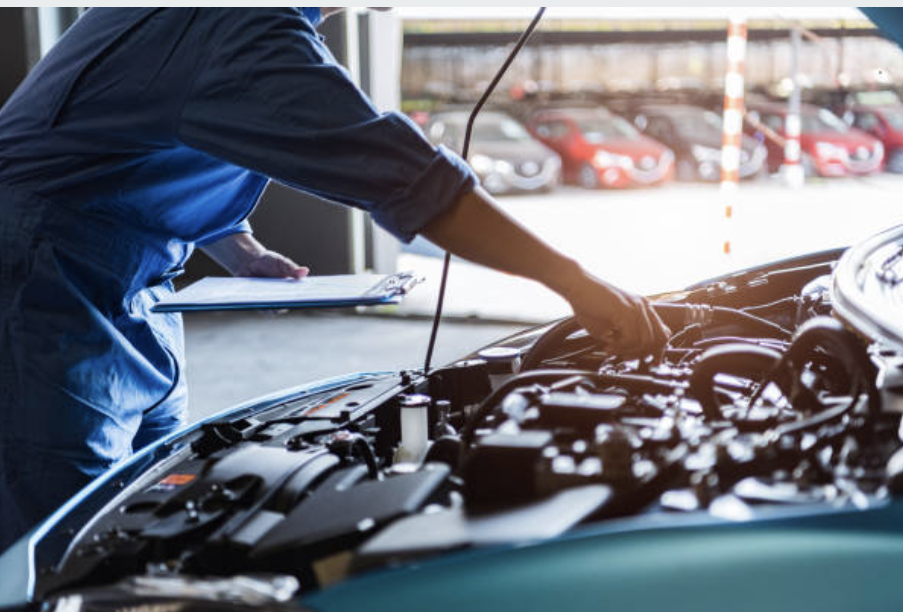
うっかりミスもなく、運転習慣にも気をつけているのにバッテリーが上がる…。その場合は、車を構成する部品の寿命や故障が原因である可能性が高まります。これらはドライバー自身では気づきにくいため、特に注意が必要です。
バッテリー本体の寿命と劣化
バッテリーは消耗品です。充放電を繰り返すうちに、内部の電極板が劣化したり、化学反応を起こす能力が低下したりして、徐々に電気を蓄える力が弱まっていきます。
バッテリーの寿命は、車の使用状況や環境によって大きく異なりますが、一般的に2年~5年と言われています。
- ・ちょい乗りが多い、電装品を多用する → 寿命は短くなる(2~3年)
- ・毎日適度な距離を走行する、メンテナンスを欠かさない → 寿命は長くなる(4~5年)
特に、最近増えているアイドリングストップ車専用のバッテリーは、頻繁なエンジン始動に耐える高性能なものですが、その分負担も大きく、寿命が比較的短い傾向にあります。
バッテリーは、寿命が近づくといくつかのサインを発します。
- ・エンジンのかかりが悪い
キーを回した時の「キュルキュル」という音が以前より長い、弱々しい。 - ・ヘッドライトが暗く感じる
アイドリング時にライトが少し暗くなり、アクセルを踏むと明るくなるような場合、発電に頼っている証拠です。 - ・パワーウィンドウの動きが遅い。
- ・バッテリー液の減少や本体の膨らみ
開放型のバッテリーの場合、液量が規定値を下回っている。また、側面が膨らんでいる場合は末期症状であり、非常に危険です。 - ・バッテリーのインジケーターの色
バッテリー上部に点検窓(インジケーター)がある場合、その色で状態を確認できます。「良好(緑)」、「要充電(白/透明)」、「要交換(赤)」など、メーカーによって異なります。
前回の交換から2年以上経過し、これらのサインが見られる場合は、バッテリーの寿命が近いと考え、早めの点検・交換を検討しましょう。
発電機の故障「オルタネーターの不具合」
いくら新品のバッテリーに交換しても、頻繁にバッテリーが上がる場合、最も疑われるのが「オルタネーター」の故障です。
オルタネーターは、エンジンの回転を利用して発電する「発電機」です。ここで作られた電気が、走行中の電装品を動かし、同時にバッテリーを充電しています。つまり、オルタネーターが故障すると、車は発電能力を失い、バッテリーの電気を一方的に消費し続けるだけになってしまいます。
この状態では、新品のバッテリーでも1~2時間も走行すれば、蓄えた電気を使い果たしてしまい、エンジンが停止してしまいます。
オルタネーターの故障には、いくつかの前兆があります。
- ・バッテリー警告灯(充電警告灯)の点灯
メーターパネルにある、バッテリーの形をした赤いランプが点灯または点滅します。これは「正常に充電されていませんよ」という車からの最も分かりやすい警告です。 - ・異音の発生
エンジンルームから「ウィーン」「ゴロゴロ」といった、普段は聞こえない異音が発生することがあります。これは内部のベアリングが摩耗しているサインです。 - ・走行中のヘッドライトのチラつきや電装品の不具合
走行中に電力が不安定になり、ライトが暗くなったり、オーディオが切れたりします。
バッテリー警告灯が点灯した場合は、走行不能に陥る危険性が非常に高いため、速やかに安全な場所に停車し、ロードサービスや修理工場に連絡してください。
忍び寄る電気泥棒「漏電(リーク)」
暗電流(待機電力)は正常な状態でも流れていますが、何らかの異常で、本来よりもはるかに多くの電気が常に流れ出てしまっている状態を「漏電(リーク)」と呼びます。まさに、車の中に“電気泥棒”が潜んでいるような状態です。
この場合、一晩でバッテリーが上がってしまうことも珍しくありません。
- ・後付けの電装品
ドライブレコーダー、カーナビ、オーディオ、セキュリティシステム、ETCなどを後から取り付けた際に、配線処理が不適切だと漏電の原因になります。特に、常時電源に接続するタイプの機器は注意が必要です。 - ・配線の劣化・損傷
長年の使用による配線コードの被覆の劣化や、事故の修理跡、ネズミなどの小動物による損傷などが原因で、配線がボディの金属部分に触れて漏電することがあります。 - ・電装品自体の内部故障。
漏電の特定は専門的な知識と道具が必要なため、個人で原因を突き止めるのは困難です。バッテリーを交換してもすぐに上がってしまう、後付けの電装品を付けてから調子が悪い、といった場合は、ディーラーや電装系に強い修理工場に相談しましょう。
その他の部品の故障(レギュレーター、配線トラブルなど)
オルタネーターで発電された電気は、電圧が高すぎるとバッテリーや他の電装品を壊してしまいます。この電圧を適切に調整しているのが「レギュレーター」という部品です。レギュレーターが故障すると、充電が正常に行われなくなり、バッテリー上がりの原因となります。(最近の車ではオルタネーターに内蔵されていることが多いです)
また、バッテリーのプラス端子とマイナス端子の接触不良や腐食、アース不良など、単純な配線トラブルが原因で充電効率が落ちているケースもあります。
【季節・環境編】特定の条件下で起こりやすいバッテリー上がりの原因
車のコンディションだけでなく、季節や外気温もバッテリーの性能に大きな影響を与え、バッテリー上がりの引き金になることがあります。
冬場(寒い時期):バッテリー性能が著しく低下する季節
「冬になるとバッテリーが上がりやすい」というのは、多くのドライバーが経験的に知っている事実です。JAFの出動統計を見ても、冬場のバッテリートラブルは突出して多くなっています。
バッテリーは、内部の電解液(希硫酸)と電極板(鉛)の化学反応によって電気を発生させています。この化学反応は、温度が低いと著しく鈍くなります。つまり、寒い環境ではバッテリーが本来持っている性能を十分に発揮できなくなるのです。
例えば、外気温が25℃の時に100%の性能を発揮できるバッテリーも、0℃では約80%、-20℃では約50%まで性能が低下すると言われています。
さらに悪いことに、冬場はエンジンオイルも硬くなっているため、エンジンを始動させるのにより大きな力(電力)が必要になります。
つまり冬場は、「バッテリーの性能は低下しているのに、要求される仕事量は増える」という、非常に過酷なダブルパンチ状態に陥るのです。これが、弱ったバッテリーが冬の朝に突然寿命を迎える大きな理由です。
夏場(暑い時期):エアコンの多用と高温による劣化
冬ほどではありませんが、夏場もバッテリートラブルが多い季節です。その原因は主に2つあります。
- エアコンの多用による電力消費の増大
夏のドライブに不可欠なエアコンは、車の中でも特に消費電力の大きい電装品の一つです。コンプレッサーを動かすために常に電力を使い、特に渋滞中のアイドリング時などは、発電量が消費量に追いつかず、バッテリーに大きな負担をかけ続けます。 - 高温によるバッテリーの劣化促進
バッテリーは極端な高温にも弱いという性質があります。エンジンルーム内は非常に高温になり、夏の炎天下では70~80℃に達することもあります。このような高温環境に晒され続けると、バッテリー内部の化学反応が過剰に進み、電極板の劣化を早めたり、バッテリー液が蒸発しやすくなったりします。
夏に受けたダメージが蓄積し、気温が下がってきた秋口や冬の初めにバッテリー上がりとして表面化することも少なくありません。

もう繰り返さない!バッテリー上がりを防ぐための予防策とメンテナンス
これまで見てきたように、バッテリー上がりの原因は様々です。しかし、その多くは日々の少しの心がけと、適切なメンテナンスで防ぐことが可能です。突然のトラブルで立ち往生しないために、今日から実践できる予防策をご紹介します。
降車時の「指差し確認」を習慣にする
うっかりミスを防ぐ最も確実な方法は、確認の習慣化です。電車や工場の現場で行われている「指差し確認」を、自分の車でも取り入れてみましょう。
車を降りてロックする前に、
- ・「ヘッドライト、OK!」(消灯を確認)
- ・「ルームランプ、OK!」(消灯を確認)
- ・「ドア、OK!」(全てのドアがしっかり閉まっているか確認)
と声に出して確認するだけでも、ミスは劇的に減ります。
バッテリーに優しい運転を心がける
- ・定期的に30分以上走行する
「ちょい乗り」が多い方は、意識的に週末にでも少し長めのドライブ(30分~1時間程度)に出かけ、バッテリーを十分に充電させてあげましょう。 - ・エンジン停止中の電装品使用は控える
待ち合わせなどで車内にいる時は、カーナビやオーディオの使用は必要最低限にしましょう。 - ・渋滞中は電装品を意識する
渋滞でノロノロ運転が続く場合は、エアコンの設定温度を少し上げる、スマホの充電を一時的にやめるなど、消費電力を抑える工夫をするとバッテリーへの負担を軽減できます。
定期的なバッテリー点検のススメ
車の健康診断と同じように、バッテリーも定期的な点検が不可欠です。
- ・インジケーターの確認
バッテリー上部の点検窓の色を定期的に見る癖をつけましょう。 - ・電圧計での測定
カー用品店などで手に入るシガーソケットに挿すタイプの簡易的な電圧計でも、おおよその状態は把握できます。エンジン停止時で12.5V以上、エンジン始動後(アイドリング時)で13.5V~14.5V程度あれば概ね正常です。停止時の電圧が12V前半に落ち込んでいる場合は、弱っているサインです。
最も確実なのは、ガソリンスタンドやカー用品店、ディーラーなどでプロに点検してもらうことです。専用のテスターを使えば、電圧だけでなく、バッテリーの内部抵抗やCCA(コールドクランキングアンペア:低温時の始動性能)といった、より詳細な性能を測定できます。これにより、バッテリーの劣化具合を正確に診断し、寿命を予測することが可能です。オイル交換などのタイミングで、年に1~2回は点検してもらうことを強く推奨します。
バッテリーの適切な交換時期を見極める
「まだ使えるから」と寿命を超えてバッテリーを使い続けるのは、バッテリー上がりのリスクを常に抱えながら走っているのと同じです。
- ・使用年数
前回の交換から3年以上経過している場合は、次の車検時や冬を迎える前に交換を検討しましょう。 - ・点検結果
プロの点検で「要交換」と診断された場合は、速やかに交換しましょう。 - ・劣化のサイン
エンジンのかかりが悪いなどのサインが見られたら、交換の時期です。
バッテリー交換の費用を惜しんだ結果、出先でのトラブル対応でレッカー代や緊急作業費がかかり、かえって高くついてしまうケースは少なくありません。予防的な交換が、結果的に時間と費用の節約に繋がります。
アイドリングストップ車ならではの注意点
アイドリングストップ車は、信号待ちなどで頻繁にエンジンを停止・再始動するため、バッテリーには非常に大きな負担がかかります。そのため、耐久性や充電受入性能が高い「アイドリングストップ車専用バッテリー」が搭載されています。
この専用バッテリーは、一般的なバッテリーよりも高価ですが、必ず適合したものに交換する必要があります。安価な標準バッテリーを装着すると、早期の性能低下やバッテリー上がりを招くだけでなく、アイドリングストップ機能が正常に作動しなくなります。また、寿命も標準車より短い傾向にあるため、よりこまめな点検が重要です。
まとめ:バッテリー上がりの原因を理解し、安心のカーライフを
今回は、車のトラブルの王様ともいえる「バッテリー上がり」について、その原因を多角的に掘り下げてきました。
- ・うっかりミス
ライトの消し忘れや半ドアなど、少しの注意で防げる原因。 - ・運転習慣
「ちょい乗り」や長期放置など、知らずに行っているバッテリーへの負担。 - ・劣化・故障
バッテリー本体の寿命や、オルタネーターなどの関連部品の不具合。 - ・季節・環境
性能が低下する冬場や、酷使しがちな夏場。
このように、バッテリー上がりの原因は一つではなく、様々な要因が複雑に絡み合って発生します。しかし、それぞれの原因を正しく理解すれば、何をすべきかが見えてきます。
降車時の確認を習慣づけ、バッテリーに優しい運転を心がけ、そして何よりも定期的な点検と予防的な交換を行うこと。これが、突然のバッテリー上がりに見舞われないための、最も確実で効果的な方法です。
この記事が、あなたのカーライフから「バッテリー上がりの不安」を取り除き、より安全で快適な毎日を送るための一助となれば幸いです。車の心臓部であるバッテリーをいたわり、突然の沈黙に慌てることのない、スマートなドライバーを目指しましょう。

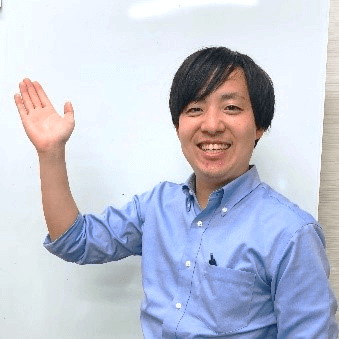
- 出身地
- 埼玉県所沢市
- 担当部署
- リテール営業
- 略 歴
- 2019年にオートアベニューへ転職入社。
「お客様に寄り添う」をモットーに、快適なカーライフの提供に邁進中。新車、中古車、車検などの整備についての最新情報を発信!お客様からの「ありがとう。」を糧に毎日を全力で駆け抜けています!

- 出身地
- 東京都西東京市
- 役 職
- 株式会社オートアベニュー 代表取締役社長
- 略 歴
-
1995年~1996年 オートアベニューでアルバイトをする
1997年~2002年 夫の仕事の関係で5年間オーストラリアへ
2002年4月~ 帰国後 株式会社オートアベニュー入社
2005年 株式会社オートアベニュー 専務取締役 就任
2008年 株式会社オートアベニュー 代表取締役社長 就任 今に至る
車業界歴約30年。現在100年に一度の変革期と言われている車業界、EV化・自動運転・空飛ぶ車などに加え、車検法などの各種法律関係で多くの法改正が行われています。
今まで学んだ多くの事や車業界界隈の様々な事をわかりやすく、皆様にお伝えいたします。