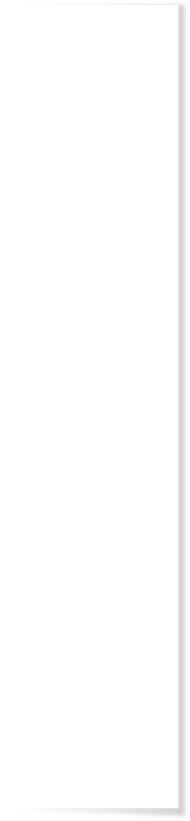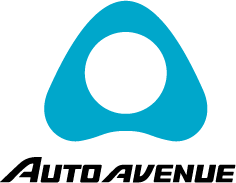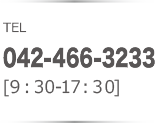車検前に必ずチェック!ヘッドライトの検査基準とメンテナンス完全ガイド

車のヘッドライトは、夜間や悪天候時に前方の視界を確保し、対向車や歩行者に自車の存在を知らせる重要な照明装置です。主に以下のような種類や機能があります。
目次
ヘッドライトの種類
光源の種類
ハロゲンランプ
- 最も一般的で安価なライト
- 発熱が多く、寿命が短め(約500~1000時間)
HID(キセノン)ランプ
- ハロゲンより明るく、寿命が長い(約2000~3000時間)
- 消費電力が少なく、青白い光を発する
LEDライト
- 高寿命(約15000時間以上)、省エネ
- 発光が早く、デザインの自由度が高い
レーザーヘッドライト
- 非常に明るく、遠くまで照らせる(高級車向け)
- 高価で複雑な構造
配光の種類
ロービーム(すれ違い用灯火)
- 対向車や歩行者を眩惑させないように配光
- 市街地や対向車がいるときに使用
ハイビーム(走行用灯火)
- より遠くを照らすため、暗い道路で使用
- 対向車や前走車がいる場合はロービームに切り替える必要あり
ヘッドライトの機能
オートライト
周囲の明るさに応じて自動で点灯・消灯
アダプティブヘッドライト
ハンドル操作に合わせて光軸を調整し、コーナーを照らす
オートハイビーム
対向車や前走車を検知し、自動でハイビームとロービームを切り替える
デイタイムランニングライト(DRL)
昼間に点灯し、他車や歩行者に自車の存在を知らせる(欧州や北米では義務化)
ヘッドライトは安全運転に欠かせない重要な装備なので、定期的な点検やメンテナンスが推奨されます。

車検とヘッドライトの関係
車検は安全な運転を確保するための重要な制度ですが、その中でもヘッドライトは特に注意が必要な項目の一つです。ヘッドライトの状態によっては車検に通らないことがあるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
ヘッドライトの重要性
ヘッドライトは単なる照明装置ではなく、運転の安全性に直結する重要な部品です。以下の理由から、ヘッドライトの適切な管理が求められます。
夜間や悪天候時の視認性向上
ヘッドライトは夜間走行時や雨・霧・雪といった悪天候時に、前方の視界を確保する役割を果たします。適切な明るさと照射範囲がなければ、障害物や歩行者を見落とすリスクが高まります。
他の車両や歩行者へのアピール
ヘッドライトは自車の存在を他の車両や歩行者に知らせる役割もあります。特に夕暮れ時やトンネル内では、周囲に自車の位置を認識させることで事故を防ぐ効果があります。
交通ルールの遵守
道路交通法では、夜間走行時にはヘッドライトの点灯が義務付けられています。また、近年ではオートライト機能が義務化され、薄暗い環境では自動的に点灯する仕様となっています。
車検の合否に影響
ヘッドライトの光量や光軸、レンズの透明度が基準を満たしていない場合、車検に通らない可能性があります。定期的なメンテナンスを行い、適正な状態を維持することが重要です。
車検におけるヘッドライトのチェック項目

光量(明るさ)
・基準値:1灯あたり6,400カンデラ以上の光度が必要です。
・測定方法:ヘッドライトから照射される光が、リフレクターで反射された状態で測定されます。
・注意点:レンズの黄ばみや曇り、リフレクターの劣化が高度不足の原因となります。
ヘッドライトの光量が基準を満たしていないと、視界が不十分になり事故のリスクが高まります。長年使用していると劣化し、暗くなることがあるため、事前に測定しておくことをおすすめします。車検では最低限の光量基準が設けられており、基準に満たない場合は不合格となるため、バルブの交換やクリーニングが必要になることがあります。
光軸(向き)
・検査内容:ロービームの照射範囲が適切かどうかを確認します。
・ポイント:左側通行の日本では、左肩上がりのカットラインが求められます。
・調整:バルブ交換や衝撃によって光軸がずれることがあるため、車検前に調整が必要です。
ヘッドライトが正しい方向を向いていないと、前方の視認性が悪くなったり、対向車のドライバーを眩惑させる原因になります。光軸がずれていると、道路を適切に照らせず、夜間走行時の安全性が低下します。車検では専用の測定機器で光軸が適正範囲に収まっているかが確認されるため、事前に整備工場で調整してもらうと安心です。
レンズの黄ばみ・汚れ・割れ・浸水(結露)
ヘッドライトのレンズが黄ばんだり汚れたりしていると、光の透過率が低下し、光量不足の原因になります。特に紫外線や経年による劣化によってレンズが変色すると、光が拡散してしまい、視界が悪くなることもあります。車検時にはレンズの透明度が確認されるため、定期的なクリーニングや研磨、コーティングのメンテナンスを行うことが推奨されます。
ハイビーム・ロービームの作動
ハイビーム・ロービームが正常に作動するかどうかも車検ではチェックされます。特に、片側が点灯しない、点灯に時間がかかる、明るさにムラがあるなどの不具合がある場合は、バルブの交換や電気系統の修理が必要になります。また、最近の車両ではオートライト機能が搭載されていることが多いため、その機能が正常に作動するかどうかも確認しておくと良いでしょう。
色温度(光の色)
・許容範囲:白色または淡黄色のヘッドライトが認められています
・注意点:青白すぎるライトや、黄色が強すぎるライトは不適合となる可能性があります。
車検ではヘッドライトの色温度(光の色)にも基準があります。一般的には白色または黄色の光が認められており、極端に青みがかったライトや赤みのあるライトは基準を満たさず、車検に通らない場合があります。HIDやLEDライトを使用している場合は、純正仕様の色温度に近いバルブを選ぶことが重要です。
ヘッドライトの固定状態
ヘッドライト本体がしっかりと固定されているかも車検でチェックされるポイントです。振動や衝撃でヘッドライトがぐらついている場合、光軸が安定せず、適正な照射範囲を確保できない可能性があります。ヘッドライトがしっかりと取り付けられているか確認し、必要に応じて固定部品の補修や交換を行いましょう。
その他のチェックポイント
- ・点灯状態:ヘッドライトが正常に点灯し、ちらつきがないこと。
- ・レンズの状態:レンズに割れや大きなキズがないこと。
- ・内部の清潔さ:リフレクターの劣化や汚れがないこと。
車検前に慌てない!ヘッドライト不備のセルフチェック術
車検が近づくと、意外と見落としがちなのが「ヘッドライト」。
「ちゃんと点いているし大丈夫でしょ?」と思っていても、実は光軸のズレや光度不足で不合格になるケースが少なくありません。
今回は、車検前に自分でできるヘッドライトチェックの方法をご紹介します。ちょっとした確認と手入れで、スムーズに車検を通すことができます。
チェック1|点灯状態の確認
まずは基本中の基本。ヘッドライトがきちんと点灯するかを確認しましょう。
- ・ロービーム・ハイビームどちらも点くか?
- ・点滅やちらつきがないか?
- ・点灯の反応が遅くないか?
このあたりは自宅でも簡単に確認できます。もし片方でも切れていれば、早めにバルブ交換を。
チェック2|レンズの状態
意外と忘れがちなのが「レンズ表面」のチェック。ヒビや曇りがあると、車検で指摘されることもあります。
- ・表面のヒビ、割れ、キズ
- ・内部の水滴やくもり
- ・レンズの透明度
特に年数が経った車は、紫外線でレンズが黄ばむことも。クリーナーやリペアキットを使えば、透明感がかなり復活します。
チェック3|色味(発光色)
ヘッドライトの色にも基準があります。車検でOKなのは「白色」または「淡い黄色」のみ。
- ・青白すぎる(6000K以上)はNGの可能性あり
- ・昔ながらのオレンジ系黄色も注意
「車検対応」と記載されたバルブを選ぶのが安心です。
最後に:万全を期すなら予備検査がおすすめ!
自分でできる範囲でチェックしても、「本当に通るかな?」と不安なときは、ガソリンスタンドや整備工場でライトの予備測定をしてもらうのがおすすめ。
1,000円〜2,000円ほどで測ってくれることもあります。
ちょっとの手間が、車検当日のトラブル回避につながります!

ヘッドライトのメンテナンス方法
定期的な清掃
ヘッドライトのレンズが汚れていると、光の透過率が低下し、明るさが十分に確保できなくなります。専用のクリーナーや柔らかい布を使って定期的に拭き、透明度を保ちましょう。ボディ用のワックスなどがヘッドライトレンズに付着すると汚れの原因となります。
レンズの黄ばみ・くもりの除去(市販の専用クリーナーがあります)
長期間使用していると、レンズが黄ばんだり曇ったりすることがあります。市販のヘッドライトクリーナーや研磨剤を使用すると、透明感を取り戻せる場合があります。また、コーティング剤を塗布することで、再発を防ぐ効果が期待できます。
バルブの交換
ヘッドライトの明るさが低下してきた場合、バルブの寿命が近い可能性があります。車検に通る光量を確保するためにも、定期的なバルブ交換が必要です。純正バルブのほか、明るさを向上させる高性能バルブへの交換も選択肢となります。
光軸の調整
ヘッドライトの向きがずれていると、前方の視認性が悪くなるだけでなく、対向車のドライバーに迷惑をかけることもあります。光軸の調整は専用の測定機器が必要なため、整備工場で点検・調整してもらうのが確実です。
ヘッドライトの内部結露対策(バルブ、配線の確実な取り付けがポイント)
ヘッドライト内部に結露が発生すると、光の透過率が低下するだけでなく、内部部品の劣化を早める原因になります。通気口の詰まりのチェックや、乾燥剤を使用することで対策できます。ダストカバーの取り付けが不完全で浸水するケースも多いです。
ヘッドライトの電気系統の点検
ヘッドライトが点灯しない場合、バルブだけでなく、配線やヒューズ、スイッチなどの電気系統の故障が原因となることがあります。異常がある場合は、専門の整備士に診てもらいましょう。
まとめ
ヘッドライトは夜間や悪天候時の視界確保だけでなく、他の車両や歩行者に対して自動車の存在を知らせる重要な役割を持っています。適切な状態を維持することで安全運転につながり、車検においてもスムーズに合格することができます。
光量が不足している場合はバルブの交換、レンズが黄ばんでいる場合はクリーニングを行うなど、定期的なメンテナンスを実施しましょう。
また、光軸のズレは対向車に迷惑をかけるだけでなく、車検不合格の要因となるため、事前に調整が必要です。ハイビーム・ロービームの切り替えが正常に動作するか、ヘッドライトの固定がしっかりしているかも確認しておくと安心です。
さらに、近年ではLEDやHIDライトが普及していますが、色温度が車検基準を満たしているかも重要なチェックポイントとなります。極端に青みがかった光は不適合となる場合があるため、適切なバルブを選ぶことが必要です。
ヘッドライトの状態を定期的にチェックし、車検前には整備工場などで確認を受けることで、より安全で快適な運転が可能となります。

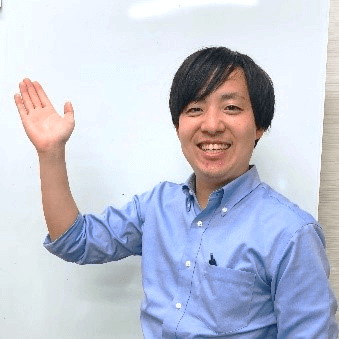
- 出身地
- 埼玉県所沢市
- 担当部署
- リテール営業
- 略 歴
- 2019年にオートアベニューへ転職入社。
「お客様に寄り添う」をモットーに、快適なカーライフの提供に邁進中。新車、中古車、車検などの整備についての最新情報を発信!お客様からの「ありがとう。」を糧に毎日を全力で駆け抜けています!

- 出身地
- 東京都西東京市
- 役 職
- 株式会社オートアベニュー 代表取締役社長
- 略 歴
-
1995年~1996年 オートアベニューでアルバイトをする
1997年~2002年 夫の仕事の関係で5年間オーストラリアへ
2002年4月~ 帰国後 株式会社オートアベニュー入社
2005年 株式会社オートアベニュー 専務取締役 就任
2008年 株式会社オートアベニュー 代表取締役社長 就任 今に至る
車業界歴約30年。現在100年に一度の変革期と言われている車業界、EV化・自動運転・空飛ぶ車などに加え、車検法などの各種法律関係で多くの法改正が行われています。
今まで学んだ多くの事や車業界界隈の様々な事をわかりやすく、皆様にお伝えいたします。